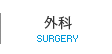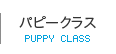歯科
歯が気になる方は石神井病院まで Tel:03-6904-7117
口臭、物を食べるときに口を気にする、頬の辺りが隆起してきた等の症状が見られた際は、口腔内疾患に罹っている可能性があります。当院では様々な口腔内疾患の治療を行っています。
担当獣医師: 石神井病院 院長 臼井義秋
日本獣医生命科学大学獣医学部外科学教室出身
ESVPS(European School of Veterinary Postgraduate Studies) 歯科口腔外科認定医
日本獣医生命科学大学外科学教室研究生
酪農学園大学付属動物医療センター腫瘍科(軟部外科)研究生
AO VET Small Animal Principle Course Yokohama 2010 修了
AO VET Small Animal Advance Course Yokohama 2012 修了
Improve International犬と猫の歯科学と口腔外科2018 修了
Fundamentals Of Dentistry(Oral Pathology, Radiology & Surgery) in Baltimore 2019 修了
歯科治療の流れ
歯科・口腔疾患の治療は、一般的に以下のような流れで治療を行います。
1.診察
身体検査を行います。次に口腔内を診察し、歯肉の状態や歯垢・歯石の付着度合い、歯の噛み合わせ、口腔内のしこりなどをチェックします。
 左上顎乳犬歯の遺残
左上顎乳犬歯の遺残 左上顎第4前臼歯の破折
左上顎第4前臼歯の破折
2.術前検査
犬や猫の歯科処置・口腔内手術を実施するには全身麻酔が必要です。全身麻酔下での処置・手術が可能かどうか、血液検査やX線検査などの健康診断を行い、健康状態や基礎疾患の有無、およびその程度を確認します。
3.手術の予約
歯科処置の手術は予約制です。
術前検査で基礎疾患が認められた場合、状況によっては歯科処置の実施が不可能となることがあります。その基礎疾患が治療によって改善あるいは軽減され、全身麻酔下での処置が可能となれば、歯科処置を実施することができます。
4.口腔内の精査
麻酔をかけた後、歯周プローブを用いて歯肉の炎症の程度、歯垢や歯石の付着度合い、歯の動揺の有無や、歯周ポケットの深さなどの口腔内の状態を検査します。
 歯周プローブによるプロービング
歯周プローブによるプロービング
5.口腔内レントゲン検査
麻酔下で口腔内の詳細な情報を得るためレントゲン検査を行います。
 デジタル歯科レントゲンセンサー
デジタル歯科レントゲンセンサー ポータブルレントゲン照射装置
ポータブルレントゲン照射装置 口腔内レントゲン写真
口腔内レントゲン写真
撮影した口腔内のレントゲン画像腹部や胸部を撮影する一般的なレントゲンと比較して、歯とその周囲組織の鮮明な画像を得ることが可能です
6.歯科治療・手術
当院では手術・治療の質の向上のために拡大鏡を用いて、歯科治療を行っています


Heine社の双眼ルーペはガラス製レンズ、色収差補正レンズを使用しており、術野を拡大することで幅広い作業域と明るく鮮明で広い視野を確保することができます。またHeine社の高出力白色LEDライトは同軸上に4万ルクスの明るさで映し出すライトを使用しており、口腔内の深部まで明るく、鮮明に見ることが出来ます。
口腔内検査やレントゲン検査で得られた情報を元に歯科治療・手術を行います。
 小動物歯科ユニット
小動物歯科ユニット 歯科治療に用いる器具・器材
歯科治療に用いる器具・器材
小動物歯科用ユニット高速エアタービン、マイクロモーター、超音波スケーラー、スリーウェイシリンジ、バキュームシリンジが1台に装備されています。

重度の歯周病症例多くの歯は脱落し、残存歯歯石歯垢が重度に沈着しています

残存歯の抜歯を行い、上顎犬歯抜歯窩を閉鎖するための歯肉粘膜フラップを作成し縫合しました
7.ルートプレーニング・ポリッシング
仕上げのクリーニングのために歯肉縁下のルートプレーニングや歯表面の研磨(ポリッシング)を行います。

ポリッシングラバーカップと研磨剤を用いて歯面の研磨を行います


■歯科治療前と治療後
上の写真は同一症例です。歯石と歯垢が付着していた歯面が光沢を取り戻し、口腔内は清潔になりました。
8.ホームデンタルケア
口腔内の健康状態を保つ最良の方法は、ご自宅での日々の歯磨きです。少しづつ慣れさせ、上手に歯磨きできるようにトレーニングしていきましょう。
重度の歯石沈着と歯周炎。歯肉は化膿しており、臼歯の多くは周囲組織の破壊が進み動揺しています。
3歳以上の犬や猫の80%には何らかの歯周病(歯肉炎/歯周炎)があると言われています。
歯周病とは
唾液成分や食物残渣のタンパク質、口腔内細菌(好気性菌)により、歯の表面(エナメル質)に歯垢が形成されます。歯垢は数日かけて分厚くなり石灰化して歯石を形成します。歯石は蓄積していくと歯肉を刺激し、歯肉縁下では酸素が不足し嫌気性細菌が増殖するようになり、歯肉炎を起こし歯肉に発赤が見られます。歯肉炎が進行していくと、歯肉縁下の嫌気性細菌が作り出す内毒素(エンドトキシン)が歯周囲の組織破壊と骨の吸収を示す歯周炎を引き起こします。歯周炎による組織破壊が進行すると、顎骨の骨吸収による骨折、鼻と口腔に病的連絡路が形成されてしまう口腔鼻腔瘻や眼の下の皮膚が貫通し膿を排出する根尖膿瘍/外歯瘻を引き起こすことがあります。
治療
重症度により様々ですが、軽度の歯肉炎の場合はスケーリング処置を行います。重度の歯周炎の場合はスケーリング処置に加えて、感染病巣の排除のために、周囲組織が破壊されている歯の抜歯を行います。いずれにせよ、日々のデンタルケアが非常に重要です。
 スケ―リング前
スケ―リング前 スケ―リング後
スケ―リング後
症例
ビーグル 8歳 去勢雄
以前から歯石の沈着が軽度に認められました。麻酔科にて、口腔内レントゲン検査を行いましたが、大きな異常はありませんでした。歯肉炎と臼歯に比較的歯石沈着が認められたためスケーリング、ルートプレーニング、ポリッシングを行いました。 歯科治療前
歯科治療前 歯科治療後
歯科治療後
歯の根元の部分(根尖部)に感染性の炎症が起こり、膿が貯まる病気で、犬の眼下の排膿/瘻管形成としてしばしば認められます。歯の破折や齲歯、咬耗などにより歯髄が露出し、感染性歯髄炎を起こした場合や歯周病の根尖部への波及により生じます。細菌感染が全身に及ぶと他の臓器が侵されることもあります。治療は、感染病巣の排除のために関連歯の抜歯とスケーリング(歯石除去)、抗菌剤や消炎鎮痛剤の投与を行います。
根尖膿瘍(外歯瘻)の症例
ポメラニアン 12歳
避妊雌慢性的に左の眼下の腫脹と排膿を認め、内科療法に反応するも繰り返すとのことで受診されました。
プロービングと口腔内レントゲン検査の結果、左上顎第4前臼歯の根尖周囲病巣から、皮膚に波及した外歯瘻と診断しました。

同歯の開放性の抜歯を行い、抜歯窩のデブリードと洗浄を行い、歯周粘膜フラップを用いて閉創しました。
猫の歯肉口内炎は、歯肉だけではなく、歯槽粘膜、頬粘膜、口腔尾側粘膜、症例によっては舌や口唇、扁桃や口蓋に及ぶ炎症や肉芽組織の増殖が生じる疾患です。
症状
口腔粘膜の痛みや不快感が激しいため、食事中に鳴き叫んだり、過剰な涎、口臭、出血、食欲不振、嚥下障害などが認められます。
原因
本症は、ウイルスや細菌などの微生物や、免疫異常などが考えられてますが、根本的な原因はわかっていません
治療方法
内科的治療に使用される薬剤は、消炎剤、鎮痛剤、抗菌薬、インターフェロンやシクロスポリンが一般的に使用されています。痛みや炎症の軽減には効果的です。
外科的治療
抜歯による外科的治療が完治や改善が認められる効果的な治療法とされています。一部の難治性症例では、抜歯後も長期の内科治療の継続を要する場合もあります。
猫の歯肉口内炎の症例
症例1
雑種猫 5歳 避妊雌
長期に及ぶな歯肉炎、口内炎および歯肉からの出血を主訴に来院されました。院内では、過剰な流涎と粘膜部位からの出血、右の口蓋舌弓粘膜に顕著な腫脹が認められました。全臼歯抜歯および、腫脹部の粘膜の切除を行いました。
病理組織診断:形質細胞性口内炎
抜歯後4ヶ月間臨床症状の改善が認められましたが、炎症の持続が尾側口腔粘膜や残存している犬歯周囲に認められたため全顎抜歯(犬歯を含めた全ての歯の除去)を実施しました。全顎抜歯後2週間で顕著な炎症の消退と食欲・全身状態の改善が認められました。
 手術前
手術前 全顎抜歯後2週間
全顎抜歯後2週間
歯が気になる方は石神井病院まで Tel:03-6904-7117